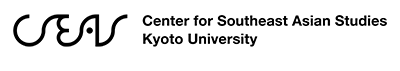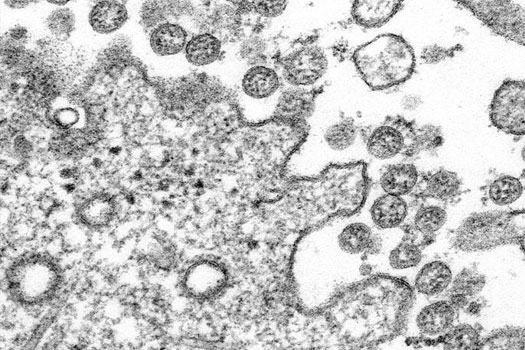本稿の英語版の公開から約1ヶ月が経過し、7月になったが、世界中から報告される新型コロナウィルス感染者の数は増え続けている。2020年1月頃からの「史料」を読み返してみると、顛末の奇妙さや変化の速さに驚かされる。だが、我々は今でも渦中にいる。一般民衆を嘲笑するのも、政府をバッシングするのも、歴史家である私には早すぎるように見える。
ただ、現時点での北部ミンダナオについては、はっきりと言えることがある。それは、コロナウィルス自体よりも、防疫体制が社会にもたらした影響の方が大きいということだ。東ティモールやインドネシア外島の多くと同様に、フィリピンのミンダナオの人々は1月以来のメディアと政府機関からのコロナウィルスに関する情報を深刻に捉えており、且つ実際に感染が報告された時期が3月と比較的遅かった。この点でフィリピンのルソン島、シンガポール、インドネシアのジャワ島や米国のニューヨークと比べた場合、有利にコロナ対策を進めることができた。本稿では、一般市民の草の根保守的な動きに着目しつつ、ミンダナオ社会が防疫体制を構築する中でどのような変化が起きたかについて、できるだけありのままに書きたい。
北部ミンダナオ、人口70万人の都市であるカガヤン・デ・オロ市にあるプエルトという町が私の実地調査の拠点である。妻の出身地だということもあり、10年来この町に親しんでおり、昨年からはここでオーラルヒストリーを集めている。カガヤン・デ・オロは、17世紀以降ミンダナオにおけるスペイン植民者の拠点の一つであったが、現在の人口の大多数は、20世紀のルソンやビサヤ諸島からの移民者たちに起源を持つ(Tigno 2006)。プエルトは、カガヤン・デ・オロの東側の境にあたり、島の北東部、そして内陸部のブキットヌンに向かうための扉となっている。元は沼地だったが、1930年代に隣町のブゴにデル・モンテの缶詰工場ができ、新たな居住地区としてデル・モンテ職員、漁業や海外製品の密輸などに関わる移民たちによって開拓された。
住民の多数派はカトリック教徒で、彼らに混じって様々な宗派のプロテスタントたちが生活している。この町の建設者たちは、ボホール、ネグロス、セブ、レイテ等別々の島々からやってきたこともあり、町内やキリスト教の行事は関係づくりにおいて重要だ。現在少数派となっているイスラム教徒たちの立場は微妙で、キリスト教徒であえてムスリムと交友関係を築こうとする人は少ない。2017年のマラウィの戦いで町が焦土と化して以来、イスラム教徒の避難者たちの数がカガヤン・デ・オロで増加している。またアキーノ三世の時代の麻薬取引の拡大、その後のドゥテルテ大統領による大規模な取締りもあり、町々における緊張感は増していた。
「コロナパニック」、民衆、そして防疫体制
フィリピンで最初の新型コロナ症例が発表された2020年の1月末から2月初めにかけて、イリガン、ヒノオグ、そしてカガヤン・デ・オロ等のミンダナオの多くの町では、マスクやアルコールの買い占めが起きていた。それに対し、各地の保健省職員たちは、「コロナは手洗いと1から2メートルの社会的距離の維持によって予防可能」と繰り返し発言し、マスクやアルコールの買い占めは、「大衆のパニック」と表現されていた。ミンダナオでは、今年に入ってからも殺人事件や誘拐事件が散発しており、またアフリカ豚熱ウィルス、ポリオ、デング熱等も流行っていた。紛争・疫病・自然災害に慣れていたミンダナオの人々は、コロナ対策に対して社会的に準備ができていた(増保 2020)。あるいは、普通の人々が、自分たちの細やかな生活を守ろうとして異常な社会を作り出す草の根保守的な動きを始めていた。
私達がプエルトに帰郷した2月19日頃、ミンダナオ島ではまだコロナウィルス感染者はひとりも発見されていなかった。ただ、筆者の勤務地であるシンガポールでは既に数十件の感染例が報告され始めていたこともあり、プエルト町内会からの指示で14日間自宅待機することになった。私達もこれに合意した。プエルトに住む家族や親戚たちは、コロナウィルス関連のジョークを言ってはゲラゲラと笑っていたが、私達と同じ皿から食べたり同じコップから飲もうとする者はいなかった。後から聞いた話では、ニュースでコロナ予防策について聞いていたため、我々からの感染をかなり警戒していたそうだ。後に彼らを安心させたことは、祈祷会にて預言の賜物を持つ老人が、我々の健康を証言したことだったそうだ。政府・宗教など様々なタイプの権威者たちの発言は影響力がある。
このような状況下、カガヤン・デ・オロの人々は、町内会関係者や都市部の人々も含めて、私達の家を訪問し続けていた。2月中は、誰かの誕生日の度に数十人の人々がひとつの家に集まり、又次の日には隣の家に集まるということを繰り返していた。初めて会う者たちの中には、私の「中国人的」外見をみて「彼は大丈夫なのか」という人もあったが、大多数の人々は私達に様々な行事に「貢献」することを求めていた。当時の報道としては、「唾液やくしゃみからのみ感染する可能性がある」ことが強調されていたため、症状のない私達に関しては、食器さえ共有しなければ感染の心配は無いと考えていたそうだ。
また、3月第1週にプエルトのマーケットを訪れた人たちは、まだ「いつもどおり」の混沌とした状況に出くわすことができた。自治体は、高速道路を走るトライシクルの取締りを積極的に行っていた。マーケットは、たくさんの人や違法にマーケット内で客を運ぶトライシクルで溢れかえっていた。すると、ハイウェイ側の出口方面から叫び声が聞こえてきた。「警察だ!警察が来てる!」 そして、マーケット内にいた数十のトライシクルが一斉に反対側の出口に向かって走りだす。歩行者たちも笑い出した。3月の初めには、プエルトで何者かによる交通整備員の射殺事件があったにもかかわらずだ。コロナウィルスの社会的影響と言えば、エコバッグの代わりに手作りのマスクを売り始めたストリートチルドレンたちだけだった。
3月11日頃、ミンダナオで最初のコロナウィルス感染例が報告されたことによって状況が一変した。私達はカガヤン・デ・オロ市の中心を訪れていたのだが、タクシードライバーからこのことを初めて聞いた。彼が言うには、「最初の感染者は、サウジアラビアから帰ってきたイスラム教徒の老女で、帰国後に病気になってカガヤンの病院に搬送された」とのことだった。この噂は、コロナウィルス人工説などの陰謀論と共に数日間流布していた。後のニュースで確認すると、このフィリピンで40番目、ミンダナオでは初めての症例は、ルソンでの就労からラナオへ帰郷し、肺炎患者としてイリガンの病院で診察され、最終的にはカガヤン・デ・オロの病院でコロナウィルス患者と診断されたものだった(TV Patrol、3月11日及び12日放送分;Timonera 2000)。こうした不正確な噂は人々が元々持っている先入観を反映している。
その後の展開は早かった。11日中にミサミスオリエンタル州は先手を打って急事態宣言をし、集会を禁止した(Saliring 2020)。カトリック教会も学校も集会や登校を中止した。ABS-CBNやGMAのミンダナオ地区放送局の報道は、ほぼコロナウィルス一色になった。次の日には、プエルトでも消毒用アルコールを初め、食料なども一時期売り切れとなった。ガイサーノやリムキットカイ等のモールでは、多くの店舗が入り口の警備員に消毒用のアルコールと拳銃式の体温計をもたせた。我々の居住区では、それぞれの区画がゲートに鍵をかけ、人々の流れをせき止め、消毒剤を街道に撒いた。政府によって「自由が奪われた」というより、人々はより厳重に自分たちを隔離しようとしているようだった。

写真1 “We’re are temporarily close” ゲートを閉める子供 撮影:土屋喜生
そして、16日に「一般的コミュニティ隔離措置(General Community Quarantine、以下、GCQ)」が宣言された。国際線・国内線のほぼすべてがキャンセルされた。また、「不要不急」の外出も禁止され、運用上は食料の調達だけが許容された。また、2月の「大衆のパニック」を後追いする形で、3月中旬に政府及び各地の自治体の指示でマスクの着用が義務化された。2月に先んじてマスクを確保していなかった人々は、手作りのマスクを着用したり、タオルを顔の周りに巻いて外出することとなった。
GCQ下で特に困難を極めていた地域は、2017年に戦争の舞台となり焦土と化したマラウィであり、水道設備が破壊された地域やIDPキャンプなどでは、基本的な予防措置の確保が難しくなっていた。国境なき医師団などのNGOはこのような地域を「最も脆弱な地域」と推定し、3月以降、医療援助や感染予防に役立つ情報を提供している(増保 2020)。
3月中旬の初期の感染者たちは、ルソンから帰郷した人々だった。そういった報道がされると、ミンダナオの人々は、ルソンやセブのロックダウンを支持する意見を様々な場で公表し始めた。昨年以降にタガログ語を話すギャングによる児童誘拐事件が相次いでいたこともあるのかもしれない。冗談ではあるが「ミンダナオは独立するべきだ」などと言う者たちもあった。ロックダウンへの強固な反対論が挙がったルソンに対して、カガヤンの知人たちは全てドゥテルテ大統領の決断を支持していた。普段はナショナリスティックなミンダナオのカトリック教徒たちから、ルソンの人々への不満や苦情を耳にしたのはほとんど初めてのことだった。
その後のコロナウィルスの広がりとしては、3月6日から数度に渡ってダバオで開催された闘鶏の大会を感染源としたケースが、ダバオ地域以外にもブキッドノン、コタバト、マギンダナオ、ブトゥアンなどで少なくとも43件確認されている(Arguillas 2020)。このような広がりの中心となったダバオは、「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine、以下、ECQ)」下に置かれることとなった。5月から7月までにミンダナオ全体で千件以上の感染が報告されているが、大多数は帰国した海外労働者(Overseas Filipino Workers、以下、OFW)やルソンやセブからの帰還者たちである。彼らはすぐに隔離施設に移動させられており、集団感染が報告されている一部地域(カラガやダバオなど)を除き、一般のコミュニティでは「新型コロナウィルスの脅威」を直接経験している者は少ない。
人々にとってのGCQの始まりとニュー・ノーマル=新常態の創出
新型コロナの文脈では、「ニュー・ノーマル(新常態)」というのは政府や国際機構などから与えられた言葉だ。しかし、様々な組織や一般の人々が、それぞれの仕方でニュー・ノーマルを作り出している。一般家庭の収入の減少や慣れない「社会的距離の維持」など、防疫体制の継続には明らかに問題がある。だがミンダナオの社会は、これまで問題を欠いたことがなく、過去数十年の変化で失われた「古き良き社会」、やや理想化された過去を復活させる機会としてニュー・ノーマルを利用する人々もいる。また、ニュー・ノーマルは、人々が「フィリピン的な考え方」と呼ぶものを非難するための生政治的な言説としても用いられている。こちらの文脈では、レイナルド・イレートが再構築した1902年の米軍によるコレラ対策時の「原住民」に関する言説──米比戦争と同時進行の歴史過程──からの継続性がある(Ileto 2017)。人々の日常を守ろうとする保身行動、懐古主義、そして植民地主義からの継続性などを指して、私は一般の人々の新型コロナへの反応を「草の根保守的な動き」と捉えている。
プエルトの人々は様々な形でGCQの始まりを迎えたが、新常態に適応するのは簡単なことではなかった。多くの人々がいつもどおりにスーパーマーケットや市場に行けば、すぐに「社会的距離の維持」は不可能になる。すぐに全てのモールが入場制限を行い、顧客たちに順序よく整列し、社会的距離を維持する方法を教えた。そして、4月16日には、カガヤン・デ・オロ市の自治体から外出許可証なるものが発行された。これにより、家族の中から一度に外出できるのはひとりのみということになった。人々は、徐々にマスクの正しい着用方法を学び(彼らはコロナ以前には知らなかった!)、社会的距離のとり方を学び、外出許可証を携帯することを覚えた。こうして人々が防疫体制に参加することにより、社会の中で違反者たちや「リスク」と見なされる行動や人々が可視化されていった。

写真2 外出許可証 撮影:土屋喜生
一部の年齢層にいる人々は「リスク」と見なされることとなった。特に60代以上の高齢者や21歳以下の「若者」たちは非常にストレスフルな生活を余儀なくされている。外出許可証システムの中で、彼らは一般的に外出を禁止されている。5月に入ってから、ひとりで生活しているシルバー市民に対して特例が設けられることとなった。だが、病身のパートナーと住んでいる高齢者や、障害者の子供と生活している高齢者の場合はどうだろうか。彼らはインフォーマルな仕事をするしかなく、「リスク」として危険視されながらも、ゆでたまごや焼き芋を売ったり、人によっては乞食をしている。
大学生たちにとって防疫体制の始まりはショッキングだった。ある学生が言うには、ほとんどの学生は、ウィルスのことよりも、試験や成績、夏休みの予定の心配をしていたそうだ。しかし、1ヶ月もすれば家での生活にも慣れてきて、自らも防疫体制の言説に沿って思考するようになっている。同じ学生が言うには、「防疫体制のときに大きな誕生日会を開く警察官は大人として悪い例」だそうだ。彼は、防疫体制終了後もしばらくは社会的距離を取ることを考えているという。そして、「フィリピン人の考え方では、防疫体制が終わったらすぐ大騒ぎして集まり始めるから危険だ」と付け足した。
OFWに頼っていた家庭は防疫体制によって経済的大打撃を受けている。ある家庭では、OFWとして働いていた女性が、休暇帰国中に防疫体制が始まってしまい、仕事が継続できなくなってしまった。そして家族全体の資金が回らなくなった。その姉が言っていた。
私達家族4人はほとんど妹ひとりの仕送りに頼っていたのですが、こういった事態が生じたときに生存できないということを身をもって知りました。食べ物や資金を恵んでくれる親戚がいることはとても感謝です。GCQが終わったら、私自身もフォーマルな仕事に就きたいと考えています。
コロナパンデミックの中、世界中で100万人のOFWの職務に影響が出ており、現在までで数万人が帰国している。また、ロックダウンの開始時に居住地を離れていた人々の帰還も問題となっている。これらの帰還者たちの検査・隔離が現状におけるフィリピンの防疫体制の焦点となっている。OFWからの仕送りに頼る経済も、あるいは今後変革を迫られるのかもしれない。
私がインタビューできた人たちの中には、GCQが行われて良かったという人々も複数いた。「トラブルが減った」と言うのだ。
以前は、夜間シャブ等の麻薬の売人たちが集落を歩き回っていました。親戚のうちにもそういった非合法の商売に関わって問題を起こしたり、逮捕された者がいました。ですが、GCQの間は彼らもおとなしく家にいて、麻薬から離れています。
家族の中に家出したまま行方不明になっていた子どもたちがいました。彼らについては、盗みを働いたり、あるいは性産業に関わっているのではないかという噂が立っていました。それに、警察に訴えても何もしてくれませんでした。ですが、GCQが実施された後、彼らは自ら家族の元に帰って来て一緒に過ごしています。町中を歩いてみても、ストリートチルドレンを見かけなくなりました。
このような人たちがGCQが終わった後も家族や親戚の元で「模範的な生活」を続けるという保証はないが、GCQを既に失われていた秩序を回復する機会として好意的に捉える人は多い。
このように防疫体制下での北部ミンダナオでの生活は、ある種の「団結」と「秩序」の形成を目指して変化しつつある。史料やインタビューを通して私が発見したことは、実に多くの人たちが「フィリピン的な考え方」を井戸端会議やインターネットで非難しているということだ。「フィリピン的な考え方」とされるものの中には、非行、麻薬取引、頑なさ、行儀悪さ、闘鶏、「不必要な集まり」、怠惰まで、植民地主義やドゥテルテ政権など様々な起源を持つテーマが含まれている。こうした防疫体制下での民衆の動きの背後で、軍によって反政府組織である新人民軍(New People’s Army、NPA)や麻薬売人のハンティングが続いている。私が記録できているニュースだけでも、3月以降100名近くのNPAゲリラがミンダナオで降伏、あるいは戦死したこととなっている。
歴史は、短期的な動因がもたらす変化が長期化し、大きな影響を人々に与えた例をたくさん教えてくれる。私は悩みつつ「草の根保守」と表現したが、このような世直し的な「フィリピン人的な考え方」へのバッシングが実際に何を目指しているのかより長期的な視点から、正確に見極める必要があるだろう。

写真3 プエルトのガイサーノモール前での「社会的距離の維持」の実施。5月15日
2020年7月21日 脱稿
インタビュー
- 匿名希望、カガヤン・デ・オロ、2020年5月22日
- 匿名希望、カガヤン・デ・オロ、2020年5月24日
- アメラ、カガヤン・デ・オロ、2019年8月24日
- ブレンダ、カガヤン・デ・オロ、2020年5月24日
- ドミニク、カガヤン・デ・オロ、2020年5月23日
- ドーラ、カガヤン・デ・オロ、2019年8月21日
- エマ、カガヤン・デ・オロ、2019年8月8日
- レオニラ、カガヤン・デ・オロ、2019年8月15日
- マリリン、バレンシア、2020年3月6日
- マリナ、カガヤン・デ・オロ、2020年2月28日
- モニカ、カガヤン・デ・オロ、2019年8月8日
- サラミ、カガヤン・デ・オロ、2020年5月24日
オンラインアーカイブズ
- GMNTV Streaming (Tetun) https://www.youtube.com/channel/UCr9KjDENKCwWh6kzC_i5bOg/featured
- Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center https://coronavirus.jhu.edu/map.html
- One Mindanao, GMA Regional TV https://www.gmanetwork.com/regionaltv/onemindanao
- Singaporean Ministry of Health website https://www.moh.gov.sg/COVID-19
- Timor-Leste Guide Post https://www.guideposttimor.com/
- TV Patrol North Mindanao, ABS-CBS Cagayan de Oro (Visayan Language) https://www.youtube.com/channel/UCcZ5AeRXRRL8aJZ-2-2mmPg/playlists
参考文献
- Arguillas, C. O. 2020. At Least 43 COVID-19 Cases in Mindanao Traced to Davao’s 6-Cock Derby. MindaNews, 22 April. https://www.mindanews.com/ (Accessed on 25 May, 2020).
- Demetrio, F. R. 1968. The Village: Early Cagayan de Oro in Legend and History. Cagayan de Oro City: Xavier University.
- Democracy Now! 2020. Noam Chomsky on Trump’s Disastrous Coronavirus Response, WHO, China, Gaza and Global Capitalism. 25 May. https://www.democracynow.org (Accessed on 25 May, 2020).
- Ileto, R. C. 2017. The U.S. Conquest. In R. C. Ileto (ed) Knowledge and Pacification: On the U.S. Conquest and the Writing of Philippine History, pp. 103-128. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Lagsa, B. 2020. After 18 Days of Zero Reports, CDO Records 5th COVID-19 Death. Rappler, 20 May. https://www.rappler.com/nation/261474-cagayan-de-oro-records-fifth-coronavirus-death-may-20-2020 (Accessed on 25 May, 2020).
- Manlangit, M. 2020. The Hurting Heroes: The COVID-19 Crisis and Overseas Filipino Workers. The Diplomat, 18 May. https://thediplomat.com/2020/05/the-hurting-heroes-the-COVID-19-crisis-and-overseas-filipino-workers/ (Accessed on 25 May, 2020).
- Montalván II, A. J. 2009. New Archaeological Site Discovered. Heritage Conservation Advocates, 30 September. http://heritage.elizaga.net/news/index.htm (Accessed on 25 May, 2020).
- Saliring, A. 2020. MisOr Under State of Calamity. SunStar Cagayan de Oro, 11 March. https://www.sunstar.com.ph/article/1847965 (Accessed on 25 May, 2020).
- Tigno, J. V. 2006. Migration and Violent Conflict in Mindanao. Population Review 45 (1) : 23-47.
- Timonera, B. 2020. Mindanao’s First COVID-19 Case Went Home to Lanao Sur Before Admission in Iligan Hospital and Later CDO. MindaNews, 12 March. https://www.mindanews.com/top-stories/2020/03/mindanaos-first-COVID-19-case-went-home-to-lanao-sur-before-admission-in-iligan-hospital-and-later-cdo/ (Accessed on 25 May, 2020).
- Wikipedia n.d. COVID-19 Pandemic in Indonesia. Available at https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Indonesia (All sources confirmed accessibility on 27 May 2020).
- 増保千尋 2020「日本人職員が見た途上国・感染症対策の苦難と希望──国境なき医師団「コロナ危機のいまこそ、世界に目を向けて」」『クーリエ・ジャポン』5月7日 https://courrier.jp/news/archives/197911/(2020年5月25日閲覧).
筆者紹介
土屋 喜生(つちや きしょう): シンガポール国立大学歴史学部博士研究員。専門は東南アジア現代史。東ティモールの国連選挙支援チーム(UNEST)のスタッフを務めた後、シンガポール国立大学にて修士号(東南アジア学、2013年)と博士号(歴史学、2018年)を取得。
Citation
土屋喜生(2020)「防疫体制と草の根保守――北部ミンダナオからの視点」CSEAS Newsletter 4: TBC.